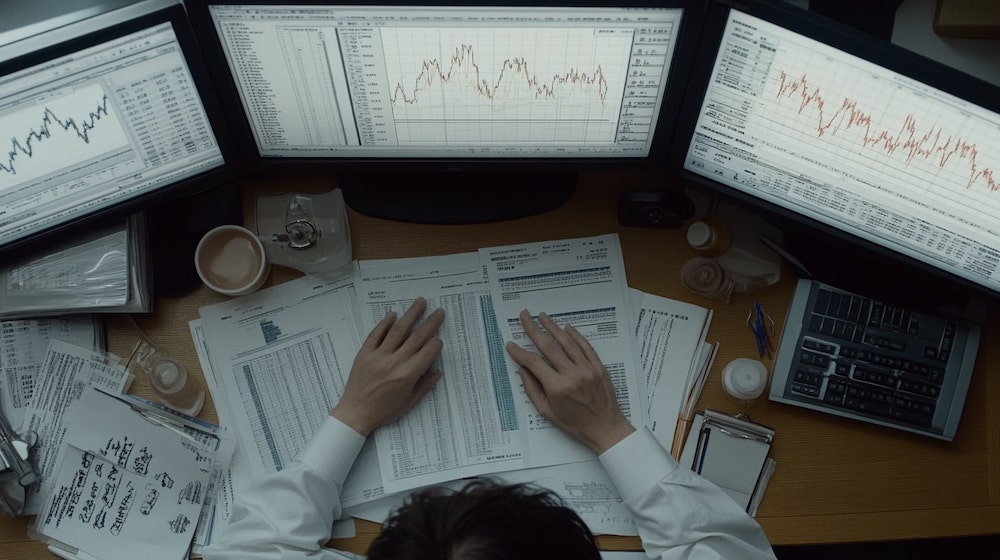知られざる歴史と進化!オリムピックナショナルGCはなぜ多くのゴルファーを惹きつけるのか
こんにちは、ゴルフライターの高橋翔です。
年間50ラウンド以上、埼玉・神奈川エリアのゴルフ場を巡る私が、今、最も注目しているゴルフ場の一つが「オリムピックナショナルゴルフクラブ」です。
「名前は聞いたことあるけど、どんなコースなんだろう?」
「都心から近いけど、本当に満足できるクオリティなの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実はこのゴルフ場、単にアクセスが良いだけではありません。
輝かしい歴史と、世界基準のコースへと進化した背景、そして地域に根差した温かいおもてなしが融合した、知れば知るほど奥深い魅力に溢れているのです。
この記事では、私が実際にラウンドし、隅々まで取材して感じたオリムピックナショナルGCのリアルな姿を、余すところなくお届けします。
こんなゴルファーにおすすめ
まずは、あなたがこのゴルフ場を楽しむのにピッタリかどうか、チェックリストで確認してみましょう。
- ✅ 都心から日帰りで、本格的なチャンピオンコースを体験したい
- ✅ 初心者から上級者まで、誰もが楽しめる懐の深いコースを探している
- ✅ プレーだけでなく、美味しい食事や充実した施設もゴルフの楽しみだ
- ✅ 戦略的なコースで、自分のゴルフ頭脳を試してみたい
- ✅ 美しい景観の中で、心からリフレッシュできる一日を過ごしたい
一つでも当てはまったなら、この記事はきっとあなたの次のラウンド計画に役立つはずです。
日帰りで充実ラウンドを楽しみたい関東圏の方へ
何と言っても最大の魅力は、そのアクセスの良さです。
私も埼玉在住ですが、思い立った時にすぐ行ける距離感は本当にありがたいですね。
初心者も中上級者も納得できる戦略的コースを探している方へ
EASTとWEST、それぞれに個性豊かなコースが用意されており、何度訪れても新しい発見があります。
レベルを問わず、全てのゴルファーが挑戦意欲を掻き立てられるはずです。
「プレー+グルメ+癒し」が揃う場所を求めている方へ
ゴルフはスコアだけが全てではありません。
仲間と語らう食事の時間、プレー後に汗を流すお風呂、その全てが最高の体験になります。
オリムピックナショナルGCは、その全てを高次元で満たしてくれます。
アクセス・料金・予約のしやすさ
川越ICから約20分!都心からのアクセス事情
オリムピックナショナルGCは、関越自動車道の「鶴ヶ島IC」から約20分、圏央道の「圏央鶴ヶ島IC」からも約13kmと、車でのアクセスが抜群です。
都心からでも1時間ちょっとで到着できるため、朝の渋滞を気にせず、ゆとりを持ってゴルフ場に向かえます。
高橋翔のワンポイント
圏央道が開通したおかげで、神奈川方面からのアクセスも格段に良くなりました。湘南エリアからでも、気軽に日帰り圏内ですよ。
平日・土日祝の料金体系とコスパ分析
料金は季節やプランによって変動しますが、公式サイトで常に最新情報が公開されています。
| 曜日 | 料金目安(セルフ・昼食付) | コスパ評価 |
|---|---|---|
| 平日 | 12,000円~18,000円 | ◎(非常に高い) |
| 土日祝 | 25,000円~35,000円 | 〇(価格相応の価値あり) |
平日は特にコストパフォーマンスが高いと感じます。
このクオリティのコースをこの価格で楽しめるのは、関東圏では非常に貴重です。
有給休暇を取ってでも、訪れる価値は十分にあります。
予約方法と混雑の傾向:狙い目の時間帯・曜日は?
予約は公式サイトのオンライン予約か、予約センターへの電話が基本です。
プレー日の2ヶ月前の同日から予約が開始されます。
人気のゴルフ場なので土日は早めに埋まりがちですが、平日の午後スルーや、月曜日は比較的予約が取りやすい傾向にあります。
私もよく、仲間との都合が合えば月曜日にラウンドを組むことが多いですね。
オリムピックナショナルGCの歴史と変遷
なぜ「オリムピックナショナル」と呼ばれるのか
このゴルフ場の歴史は、少しユニークです。
元々は「エーデルワイスゴルフクラブ」(現在のEAST)と「鶴ヶ島ゴルフ倶楽部」(現在のWEST)という、二つの異なるゴルフ場でした。
これらが統合され、2017年に「オリムピックナショナルゴルフクラブ」として新たなスタートを切ったのです。
この名称変更には、世界に通用するナショナルクラスのゴルフ場を目指すという、強い意志が込められています。
開場当初からの進化:クラブ名変更とコース改革の舞台裏
特筆すべきは、WESTコースの大規模なリニューアルです。
2017年から2020年にかけて、世界的なコース設計家であるジム・ファジオ氏の監修のもと、コースが全面的に生まれ変わりました。
ジム・ファジオ氏が日本でコース改造を手掛けるのは非常に稀なこと。
この改革により、WESTコースは戦略性と景観美が飛躍的に向上し、多くのゴルファーを惹きつける原動力となっています。
地元ゴルファーに愛され続ける理由
歴史ある二つのクラブが一つになり、さらに世界基準の改修が加わった。
しかし、根底にあるのは地元ゴルファーに寄り添う温かい姿勢です。
私もラウンド中にスタッフの方と話す機会が多いですが、クラブへの愛情と誇りを感じます。
そのアットホームな雰囲気が、リピーターを増やし続けている最大の理由かもしれません。
コースレイアウトと戦略性
各コースの個性紹介(WEST/EAST/SOUTH)
オリムピックナショナルGCは、それぞれ全く異なる顔を持つコースで構成されています。
※SOUTHコースは2024年3月末で閉鎖となりましたが、ここではEASTとWESTの魅力に迫ります。
- WESTコース(27ホール)
ジム・ファジオ設計の、ダイナミックで美しいアメリカンスタイルのコース。
「アザレア」「カメリア」「シバザクラ」の3コースからなり、池やバンカーが巧みに配置され、景観の美しさと戦略性の高さが両立しています。 - EASTコース(18ホール)
こちらは「鬼才」ピート・ダイの設計。
名物のアイランドグリーンや、うねるフェアウェイ、線路の枕木を使ったバンカーなど、独創的なデザインが特徴です。
プレーヤーの挑戦意欲を掻き立てる、スリリングなレイアウトが楽しめます。
攻め方のコツ:「あなたなら何番で狙う?」
例えば、EASTコースの名物ショートホール。
グリーンが池に囲まれており、距離は短いながらも極度のプレッシャーがかかります。
あなたなら、このホールを何番アイアンで狙いますか?
風を読み、ピンポジションを見極め、自分のクラブを信じて振り抜く。
この一打に、ゴルフの醍醐味が凝縮されています。
WESTコースでは、広々としたフェアウェイに誘われてドライバーを振り回したくなりますが、バンカーの配置が絶妙で、落としどころがスコアを大きく左右します。
ただ飛ばすだけでは攻略できない、まさにゴルフ頭脳が試されるコースです。
初心者・中級者・上級者向けのラウンド攻略プラン
- 初心者の方:まずはWESTコースがおすすめです。フェアウェイが広く、プレッシャーが少ないホールが多いので、気持ちよくプレーできます。無理せず、刻む勇気を持つことがスコアメイクの鍵です。
- 中級者の方:EASTコースに挑戦してみましょう。ピート・ダイの罠にハマらないよう、コースマネジメントを徹底することが重要です。事前にコースレイアウトをよく確認しておきましょう。
- 上級者の方:WESTコースのバックティーからのプレーは、まさにチャンピオンコースの趣です。ファジオの設計意図を読み解きながら、パーフェクトなゲームを目指してください。
自然と調和した美しい景観
グリーンの曲線美とフェアウェイの自然味
オリムピックナショナルGCを訪れて息をのむのは、その手入れの行き届いた景観美です。
特にWESTコースのフェアウェイは、まるで緑の絨毯のよう。
そして、アンジュレーション豊かなグリーンの曲線美は、それ自体が芸術品のようです。
プレーの合間にふと顔を上げると、武蔵野の豊かな自然が広がり、心が洗われるような感覚になります。
季節ごとの風景とプレーへの影響
このゴルフ場は、四季折々で全く違う表情を見せてくれます。
- 春:WESTコースのコース名にもなっているシバザクラや、アザレアが咲き誇り、コースを鮮やかに彩ります。
- 夏:深い緑と青い空のコントラストが美しく、開放的な気分でプレーできます。
- 秋:紅葉がコースを飾り、一年で最も美しい季節かもしれません。落ち葉がラフに隠れることもあるので、ボールの行方は最後までしっかり見ましょう。
- 冬:空気が澄んで、遠くの山々まで見渡せます。グリーンが硬くなるので、手前から攻めるのがセオリーです。
カメラ片手に歩きたくなるラウンド体験
本当に美しいゴルフ場なので、私はいつもスマートフォンで何枚も写真を撮ってしまいます。
特に朝日に照らされたフェアウェイや、夕日に染まるクラブハウスは格別です。
スコアカードだけでなく、思い出の写真もたくさん持ち帰れる。
そんな素敵な一日を約束してくれます。
クラブハウス・食事・サービスの満足度
地元食材を活かした人気ランチランキング
ラウンドの大きな楽しみの一つがランチですよね。
オリムピックナショナルGCは、食事のレベルが非常に高いことでも知られています。
高橋翔が選ぶ!おすすめランチBEST3(EAST)
- 陶板ステーキ:熱々の陶板で提供されるジューシーなステーキ。午後のプレーへのエネルギーチャージに最適です。
- 天せいろ蕎麦:サクサクの天ぷらと、のど越しの良いお蕎麦の組み合わせ。さっぱりと食べたい時におすすめ。
- 料理長特製カレー:じっくり煮込まれた、深みのある味わい。ゴルフ場のカレーはなぜか格別に美味しいですよね。
施設の充実度:風呂・ロッカー・売店まで
リニューアルされたWESTのクラブハウスは、モダンで高級感があり、訪れるだけで気分が高まります。
ロッカーは広々として清潔感があり、プレー後の疲れを癒すお風呂も快適そのもの。
売店も充実しており、オリジナルグッズや地元の名産品も取り揃えています。
プレー前にボールを買い足したり、お土産を選んだりするのも楽しい時間です。
接客対応・雰囲気:はじめてでも安心できる空間か?
フロントからマスター室、レストランのスタッフまで、全ての皆さんの対応が非常に丁寧で心地よいです。
名門の風格がありながらも、決して堅苦しくはなく、初めて訪れる人でもリラックスして過ごせる温かい雰囲気に満ちています。
こうしたホスピタリティの高さが、このゴルフ場の評価をさらに高めているのだと感じます。
実際に、オリムピックナショナルの口コミを詳しく解説しているこちらの記事でも、スタッフの対応やコース管理に関する高い評価が寄せられており、多くのゴルファーが満足している様子がうかがえます。
ラウンド後の過ごし方と周辺情報
近隣の立ち寄り温泉・観光スポット
プレーでかいた汗を、温泉でさっぱり流して帰るのも良いですね。
車で少し足を延せば、「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」など、日帰り入浴を楽しめる施設があります。
また、歴史ある街並みが残る「小江戸・川越」も近く、ゴルフ帰りに観光を楽しむのもおすすめです。
ゴルフ後に立ち寄れるグルメスポット
毛呂山町や鶴ヶ島市周辺には、地元で人気の美味しいお店がたくさんあります。
がっつり食べたい方向けのラーメン店や、地元の食材を使った和食店など、その日の気分に合わせて選べます。
ゴルフ仲間と反省会を兼ねて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
高橋翔おすすめ「もうひとつの楽しみ方」
私のおすすめは、EASTとWESTを日を改めて両方体験してみることです。
ピート・ダイとジム・ファジオ、二人の天才設計家の思想の違いを肌で感じることで、ゴルフの奥深さをより一層理解できます。
「昨日のEASTはこうだったけど、今日のWESTはこう攻めよう」と、戦略を練る楽しみが倍増しますよ。
まとめ
オリムピックナショナルGCの魅力を総まとめ
最後に、この記事でお伝えしたオリムピックナショナルGCの魅力をまとめます。
- 抜群のアクセス:都心から1時間強で到着できる、日帰りゴルフの最適地。
- 世界基準のコース:ジム・ファジオとピート・ダイ、二人の巨匠が手掛けた戦略性豊かな45ホール。
- レベルを問わない懐の深さ:初心者から上級者まで、全てのゴルファーが楽しめる設計。
- 最高のホスピタリティ:美しい景観、美味しい食事、心地よい接客が揃っている。
- 進化し続ける歴史:伝統を受け継ぎながら、常に最高の体験を追求し続ける姿勢。
私がこのゴルフ場に何度も足を運びたくなる最大の理由は、「挑戦と癒しの完璧なバランス」です。
コースは常に「次はこう攻めてやろう」という挑戦意欲を掻き立ててくれます。
しかし、クラブハウスに戻れば、美しい景観と温かいサービスがその興奮を優しく癒してくれるのです。
この絶妙なバランスが、ゴルファーを虜にする最大の魅力だと感じています。
もしあなたが次にオリムピックナショナルGCを訪れるなら、こんな仲間と行くのがおすすめです。
- ゴルフ好きな会社の同僚と:戦略的なコースで、チームビルディングも兼ねて。
- 大切な取引先との接待ゴルフで:施設のクオリティとアクセスの良さが喜ばれます。
- 腕前を競い合うライバルと:EASTとWEST、どちらがより良いスコアで回れるか勝負。
- ゴルフを始めたばかりの友人と:WESTコースで、ゴルフの楽しさを存分に味わってもらう。
この記事が、あなたの次のラウンド計画のきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
ぜひ、オリムピックナショナルGCで、最高のゴルフ体験を味わってみてください。